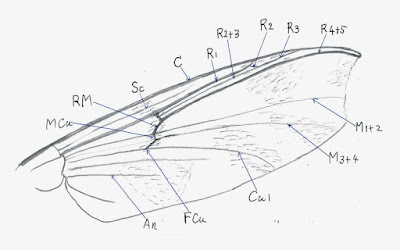先週に引き続いて、庭のクヌギにいたいもむし。
2023年4月24日
 |
| ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella |
それがつい昨日羽化した。
 |
| ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella |
 |
| ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella |
前翅長は約9㎜
 |
| ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella |
羽化後の繭
矢印側に鱗粉が付いているのでコチラから羽化した模様。ハマキガやメイガと違って繭から蛹は飛び出してこないみたいである。
円内は幼虫の脱皮殻。
なぜか繭の外にあった。
繭の斜めに裁断した部分はスリット状に隙間が開くので、蛹化する際に外に出すことができるようだ。
きれい好きなのだろうか。
さて、繭から蛹殻を引っぱり出してみた。
 |
| ウスイロクチブサガ Ypsolopha parenthesella |
あと腹端に鉤状刺毛が発達していない。
蛹は飛び出さないので、ストッパーの鉤状刺毛は必要ないのかしら。
その代わりに繭にスリットを設けて、羽化した成虫が出やすいようにしているのかもね。
おまけ
蛹の頭端
下方に向かって鋭く短いトゲが生えていた。(画像は仰向けの状態)
なんの用途に使うのやら?
ではまた